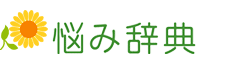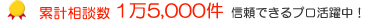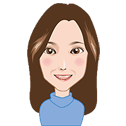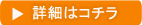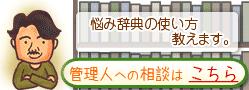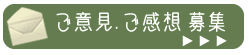相談&回答 |
約6分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間 |
回答プロ: 相楽 まりこ

初めて「鬱」と診断され、今のままの病院・治療方法でいいのか不安です。
ご相談者:40代/男性
はじめまして。
40代ではじめて“鬱”と診断をうけました男性です。
仕事で失敗が続き、社内の皆さんに申し訳ないと思いながら
もモレや不配慮・計画的な業務進行ができませんでした。
定例的な業務も実行できない為、職場では「人としてどうか」
とまで叱責され、悩みに悩んだ末先日初めて精神科にかかった
処『鬱』と診断されました。
2度ほど心療内科にかかっていて、SNNR系の軽い薬を処方
されています。
先日の診療では「気持ちが高揚する時と低下する時がある」
と先生にお話した処『躁鬱の気がある』と言われ、
その“気持ちの落差を狭める”薬が追加されました。
薬での治療については効能や“どういう風に症状を緩和する
のか”を図書館などで調べて理解はできましたが、一時的な
改善をしたとしても、根本的な『考え方の改善』をしなけれ
ば職場でもまた失敗ややる気を無くなってしまうのではと
心配になります。
・こういう考え方のクセをつけたら良い
・このように生活を変えましょう
など“今の不調を治す”だけでなく「自分の改めるべき事を
アドバイスいただき再び鬱に陥らないようにしたい」のです。
現在も日々・個々の仕事には取り組もうと努力してはいますが
計画的なプロジェクトや「●日までに自分で考えてまとめておいて」
と指示された資料がでてくると途端に憂鬱になり、会社に行け
なくなります。
(頑張って出社はしますが、頭痛などで効率的な業務ができず
期日までに資料が仕上がらず、さらに不安が募り・・・悪循環です。)
*医者に「(鬱になってから)今の調子では計画的な仕事もできず
意欲が沸かない」と相談した処
『そんなのは学生時代から問題になっているはずですょ』
と言われてしまいとくに得られるものがありませんでした。
その先生との相性が合わないのでしょうか?
セカンドオピニオンも考えるべきかどうか。
(初めての精神科医なので安易に医者を変わるのも抵抗があります。)
良いアドバイスをいただければ幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
40代/男性 | 日付:2008年11月10日(月) 12:46 JST | 閲覧件数: 2,510
まずはお医者さんと納得がいくまで話をして、自分にあった治療計画・治療方法を明確にしていくとよいのでは。
はじめまして。
このたびはご相談いただきまして誠にありがとうございます。
また、回答が遅くなりまして申し訳ありません。
相談内容を拝見いたしました。
現在心療内科にかかっておられ、そこでは『鬱』と診断されたとのことでしたね。
また、気持の高揚する時と低下する時があるという話をしたら、『躁鬱の気がある』と言われ、複数のお薬を服用されているとのことでした。
薬の効能はご自身で調べられて理解をしているが、根本的な『考え方の改善』をしなければ、というご心配をされておられるのですね。
なお、現在は憂鬱になっても頑張って出社されておられるとのこと。
でも、頭痛などで能率的な業務ができず、さらに不安が募る・・・
悪循環を感じ、非常に不安や焦りを感じていらっしゃることが伝わってきました。
そして、この悪循環とお感じになっている現状を変えるために、『考え方の改善』をしたいと思ったり、セカンドオピニオンについて検討したり、と、ご自分で色々考えていることも教えてくださいましたね。
私も、『考え方の改善』や『セカンドオピニオン』について考えるのはとても良い視点ではないかと思いましたので、この2点にわけてここでお話させていただきます。
●『考え方の改善』について
うつ病の治療において、ある程度の結果を残している「認知行動療法」という心理療法があります。
とても簡略にご説明いたしますと、「自分の今までの認知方法を改善し、物事の捉え方を変化させる」方法です。
人は誰しもその人独特の物事の捉え方だったり考え方のクセを持っており、時として、その考え方が自分の首を絞めている場合もあるというのが認知行動療法の理論です。
まずは、その自分独特の認知のクセに気づくことから始め、クセが分かったら別の考え方をするように日常の中で実践していきます。
うつ病の場合、薬も服用しながら並行で行われることが一般的だと思われます。
あなたは、相談文章の中に「こういう考え方のクセをつけたら良い」というアドバイスが欲しいと書いていました。
もしかしたら、色々とご自身でお調べになっている中に認知行動療法の情報があったのかな、とも思いましたが、いかがでしょうか。
現在、認知行動療法を行う専門家がいる病院・クリニックは増えてきています。
もしご興味をお持ちでしたらお住まいの近くで調べてみるのはいかがでしょうか。
●『セカンドオピニオン』について
まず、あなたが今受診されている病院で心配・不安に思っていることを整理してみるとします。
どんなことが不安要因なのでしょうか。
もしよろしければ、以下の3点のようなことを検討してみてください。
*薬の説明は納得がいくまでしてもらっていますか?
*あなたの悩みにきちんと耳をかたむけてもらえている感じはしますか?
*あなたがその病院に通うことでどうなりたいという治療目標を共有し、それに向けた治療計画を明確に示してくれましたか?
私は、上記の3つめは特に大切だなと思います。
お医者さんの中には、忙しくて患者の話を聞く時間を多く取れない方がいます。
こちらが遠慮していると十分に話ができずに終わり、結果としてそれが不安感や不信感につながってしまう可能性があると思います。
ですから、まずは自分で不安や疑問点をどんどん聞いてみるのがいいと思います。
遠慮せず色々尋ねてみると、自分と医者の相性も徐々に分かってくるかもしれません。
もしかしたら、不安感が解消されて信頼関係が生まれるかもしれませんし、逆に、どうも安心して治療をお任せできない、という気持ちになるかもしれません。
やはり人間同士ですから、相性はあると私は思います。
はじめての精神科医ということなので、まずはよく話をしてみることが一番だと思います。
そして、やはり別の医者の意見を聞いてみたいという気持ちが消えなければ、セカンドオピニオンを行ってみてはいかがでしょう。
セカンドオピニオンは病院にかかる人間だれもが平等に持つ権利ですから、その権利を使うことには何の問題もないはずです。
一番大切なのは、あなたが安心して治療を受けられるかどうかだと思います。
長くなりましたが、あなたの気持が少しでも軽くなるよう願っています。
相談ありがとうございました。
回答日時:2008年11月21日(金) 18:39 JSTお礼のコメントを書く
・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。
こちらのプロも相談受付中です。
悩み辞典は、安心して登録・相談できます。
※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。
※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。
※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。
※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。
※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。