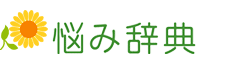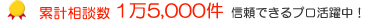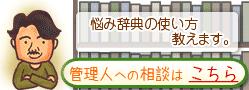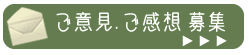相続と貴重な時間①
- 2010年2月12日(金) 15:06 JST
-
- 投稿者:
- 古家 秀樹
-
- 閲覧数
- 4,266
【 相続と貴重な時間① 】
大切な家族と別れるというのはとても寂しく、悲しいものです。
突然の別れなら、なおさらだと思います。
多くの場合、まずは心の整理をして、それから故人の残した財産等を
整理することになるのではないでしょうか?
法律には相続に関するさまざまな考え方や方法が規定されています。
その中には遺された者の生活を守るために有効な手段や
親族間で争いを防ぐ方法などもあります。
ただし、いつまでも財産を持ち主不確定のままにもしておけないため、
時間的制約も規定されています。
法律では「亡くなったとき」に相続は開始します。
そこで心の整理をしている間に、とりえた手段を逃してしまわないよう、
注意したい「手段」と「期間(時間)」についてこれからご紹介していきたいと思います。
相続における貴重な時間、
皆さん、有効に時間を使っていますか。
第2部へ続きます、、、
大切な家族と別れるというのはとても寂しく、悲しいものです。
突然の別れなら、なおさらだと思います。
多くの場合、まずは心の整理をして、それから故人の残した財産等を
整理することになるのではないでしょうか?
法律には相続に関するさまざまな考え方や方法が規定されています。
その中には遺された者の生活を守るために有効な手段や
親族間で争いを防ぐ方法などもあります。
ただし、いつまでも財産を持ち主不確定のままにもしておけないため、
時間的制約も規定されています。
法律では「亡くなったとき」に相続は開始します。
そこで心の整理をしている間に、とりえた手段を逃してしまわないよう、
注意したい「手段」と「期間(時間)」についてこれからご紹介していきたいと思います。
相続における貴重な時間、
皆さん、有効に時間を使っていますか。
第2部へ続きます、、、
相続遺言 ~エンディングノート~
- 2009年11月12日(木) 19:21 JST
-
- 投稿者:
- 古家 秀樹
-
- 閲覧数
- 4,414
〔 ~第3章(最終章)~ エンディングノートに書くこと(今後の自分の希望)〕
先回は、エンディングノートに書くこと(自分の経歴)についてお話しました。
今回は、エンディングノートに書くこと(今後の自分の希望)についてお話をします。
まずは自分の体についての希望です。
誰にどこで介護して欲しいか、延命治療の希望の有無、臓器移植の希望の有無、
どこで最期を迎えたいかなど、今後の自分の希望を書いておきましょう。
この情報があるとご家族は後々まで自分の選択について悩まずにすみます。
次に葬儀についての希望です。
宗教や宗派、喪主になって欲しい人、葬儀の希望、特別に連絡して欲しい人など、
葬儀に関わる希望やお墓の希望を書いておきましょう。特に密かに特定の宗教を
信仰している場合は、その宗教の連絡先も書いておきましょう。
そして、大切な物の保管場所、加入している保険、基礎年金番号、所有している
財産、財産の使い方についての希望などを書いておきましょう。財産の使い方の詳
細は遺言で書くことをお薦めしますが、寄附したい機関の有無や大まかな希望を書
いておきましょう。
たしかにエンディングノートを書くことは辛いことです。
しかしいつか必ず迎えるその時に、こうして欲しいというご本人の希望と、本人の
希望通りに送ってあげたいというご家族のお気持ちを1つにするためのものがエン
ディングノートです。
素晴しい最期を迎えるために、ご家族が安心して送り出せるために、是非作成し
てみて下さい。
先回は、エンディングノートに書くこと(自分の経歴)についてお話しました。
今回は、エンディングノートに書くこと(今後の自分の希望)についてお話をします。
まずは自分の体についての希望です。
誰にどこで介護して欲しいか、延命治療の希望の有無、臓器移植の希望の有無、
どこで最期を迎えたいかなど、今後の自分の希望を書いておきましょう。
この情報があるとご家族は後々まで自分の選択について悩まずにすみます。
次に葬儀についての希望です。
宗教や宗派、喪主になって欲しい人、葬儀の希望、特別に連絡して欲しい人など、
葬儀に関わる希望やお墓の希望を書いておきましょう。特に密かに特定の宗教を
信仰している場合は、その宗教の連絡先も書いておきましょう。
そして、大切な物の保管場所、加入している保険、基礎年金番号、所有している
財産、財産の使い方についての希望などを書いておきましょう。財産の使い方の詳
細は遺言で書くことをお薦めしますが、寄附したい機関の有無や大まかな希望を書
いておきましょう。
たしかにエンディングノートを書くことは辛いことです。
しかしいつか必ず迎えるその時に、こうして欲しいというご本人の希望と、本人の
希望通りに送ってあげたいというご家族のお気持ちを1つにするためのものがエン
ディングノートです。
素晴しい最期を迎えるために、ご家族が安心して送り出せるために、是非作成し
てみて下さい。
【相続人が50人!?】
- 2009年10月20日(火) 00:10 JST
-
- 投稿者:
- 古家 秀樹
-
- 閲覧数
- 2,706
【相続人が30人!?】
法律的に、原則、相続人になる権利があるのは、配偶者、子、両親、兄弟姉妹等です。
また、子が生存しているなら配偶者と子供が相続人となり、亡くなった配偶者の両親と兄弟姉妹は
相続人から外されます。
普通の一般的な家庭を想像してみると、両親と子供2人の場合、両親の一方が亡くなった場合には、
配偶者と子供2人が相続人になる可能性がありますので相続人の人数は3人という感じですよね。
相続手続というのは結構面倒です。
被相続人(故人)の名義を相続人の名義に変えるには、相続人全員が話し合って合意し、全員の署名
押印や印鑑証明が必要になってくる場合が多いのです。
まぁ、3人くらいなら多少面倒でも何とかなると思いますが、
しかし、これが30人となると…。
相続人が30人なんて、ありえない話と思われるかもしれません。
でも、ありえなくもないのです。
どういう場合かと言いますと、
相続手続をやらずに、何年も何十年もほったらかしにしていたときです。
例えば、祖父名義の相続手続きがなされていない場合に、手続きがお孫さんの代になった場合には、
10名以上の相続人が出てくることも珍しくはありません。
相続が始まったら、
お子様のためにも早めに手続をするのがいいでしょう。
法律的に、原則、相続人になる権利があるのは、配偶者、子、両親、兄弟姉妹等です。
また、子が生存しているなら配偶者と子供が相続人となり、亡くなった配偶者の両親と兄弟姉妹は
相続人から外されます。
普通の一般的な家庭を想像してみると、両親と子供2人の場合、両親の一方が亡くなった場合には、
配偶者と子供2人が相続人になる可能性がありますので相続人の人数は3人という感じですよね。
相続手続というのは結構面倒です。
被相続人(故人)の名義を相続人の名義に変えるには、相続人全員が話し合って合意し、全員の署名
押印や印鑑証明が必要になってくる場合が多いのです。
まぁ、3人くらいなら多少面倒でも何とかなると思いますが、
しかし、これが30人となると…。
相続人が30人なんて、ありえない話と思われるかもしれません。
でも、ありえなくもないのです。
どういう場合かと言いますと、
相続手続をやらずに、何年も何十年もほったらかしにしていたときです。
例えば、祖父名義の相続手続きがなされていない場合に、手続きがお孫さんの代になった場合には、
10名以上の相続人が出てくることも珍しくはありません。
相続が始まったら、
お子様のためにも早めに手続をするのがいいでしょう。
〔 ~第2章~ エンディングノートに書くこと(自分の経歴)〕
- 2009年9月30日(水) 17:40 JST
-
- 投稿者:
- 古家 秀樹
-
- 閲覧数
- 3,246
〔 ~第2章~ エンディングノートに書くこと(自分の経歴)〕
先回は、自分が亡くなった後にご家族にできるだけ迷惑をかけないために「エンディングノート」を作りましょうというお話をしました。
今回は、「エンディングノート」に書くこと(自分の経歴)についてお話します。
まずは家系図です。
自分を中心に、祖父母、両親、配偶者、子供、孫、親戚などを書きます。
亡くなった後に先妻の子供がいるとわかるなど、トラブルになるケースもありますので、すべて書いておきましょう。
次に、自分が生まれてから現在までに住んだ場所(わかれば住所)をすべて書いておきましょう。
亡くなった後は生まれてから死亡するまでの連続した戸籍が必要になりますので、この情報があるとご家族は非常に助かります。
そして、小学校、中学校、高校などの自分の母校、職歴、職場、その中で仲が良かった人、その人の連絡先を書いておきましょう。
ご家族の方がすぐに連絡できるようにするためです。また会社によっては遺族年金の手続等が必要な場合があるからです。
このような事務的なことばかりしか書かれていないノートでは、書いている本人も辛いでしょうし、残されたご家族も寂しくなってしまいですので、ご家族やお友達へのメッセージ、ご家族やお友達との思い出や写真、残されたご家族が悲しい中でもクスッと笑えるようなエピソードなども一緒に書いておかれることをお薦めします。
次回は「エンディングノート」に書くこと(今後の自分の希望)についてお話します。
先回は、自分が亡くなった後にご家族にできるだけ迷惑をかけないために「エンディングノート」を作りましょうというお話をしました。
今回は、「エンディングノート」に書くこと(自分の経歴)についてお話します。
まずは家系図です。
自分を中心に、祖父母、両親、配偶者、子供、孫、親戚などを書きます。
亡くなった後に先妻の子供がいるとわかるなど、トラブルになるケースもありますので、すべて書いておきましょう。
次に、自分が生まれてから現在までに住んだ場所(わかれば住所)をすべて書いておきましょう。
亡くなった後は生まれてから死亡するまでの連続した戸籍が必要になりますので、この情報があるとご家族は非常に助かります。
そして、小学校、中学校、高校などの自分の母校、職歴、職場、その中で仲が良かった人、その人の連絡先を書いておきましょう。
ご家族の方がすぐに連絡できるようにするためです。また会社によっては遺族年金の手続等が必要な場合があるからです。
このような事務的なことばかりしか書かれていないノートでは、書いている本人も辛いでしょうし、残されたご家族も寂しくなってしまいですので、ご家族やお友達へのメッセージ、ご家族やお友達との思い出や写真、残されたご家族が悲しい中でもクスッと笑えるようなエピソードなども一緒に書いておかれることをお薦めします。
次回は「エンディングノート」に書くこと(今後の自分の希望)についてお話します。
遺言書 その2 ~自筆証書遺言~ ニックネームでも大丈夫??
- 2009年9月17日(木) 00:02 JST
-
- 投稿者:
- 古家 秀樹
-
- 閲覧数
- 3,864
遺言書 その2 ~自筆証書遺言~ ニックネームでも大丈夫?
自筆証書遺言とは、文字通り自分で筆記して作成する遺言です。
紙と筆記用具さえあれば、だれでも簡単に作成することが出来ます。
ただし、誰でも簡単に作成できるという利点がある反面、
必要事項を記入漏れ等で無効となるケースもあり、中途半端な作成
では確実性に乏しいと言えるでしょう。
では、自筆証書遺言作成で注意すべきこととは何なのでしょうか?
自筆証書遺言の大まかな注意事項は以下の通りです。
・遺言の内容はすべて自筆で書く。
人に書いてもらったものは無効となります。
パソコンで作成は大丈夫??
・遺言の内容には曖昧な表現を使わない。
誰が見てもわかるように書きましょう。
土地・建物・預金など、誰に何をどれだけあげるのかを明確にしましょう。
・遺言を作成した日付、自分の名前を必ず記入し、押印する
(実印でなくても良いが、実印が好ましい)
名前の記載は、芸名でもニックネームでも大丈夫??
日付の記載は、平成21年9月末日でも大丈夫??
無効にならない自筆証書遺言を作成したいのであれば、
自筆証書遺言作成後に専門家に添削してもらいましょう。
せっかく遺言書を書いたのに無効になってしまったら意味がありませんよね?
次回は自筆証書遺言より安心・確実な公正証書遺言について紹介していきたい
と思います。
自筆証書遺言とは、文字通り自分で筆記して作成する遺言です。
紙と筆記用具さえあれば、だれでも簡単に作成することが出来ます。
ただし、誰でも簡単に作成できるという利点がある反面、
必要事項を記入漏れ等で無効となるケースもあり、中途半端な作成
では確実性に乏しいと言えるでしょう。
では、自筆証書遺言作成で注意すべきこととは何なのでしょうか?
自筆証書遺言の大まかな注意事項は以下の通りです。
・遺言の内容はすべて自筆で書く。
人に書いてもらったものは無効となります。
パソコンで作成は大丈夫??
・遺言の内容には曖昧な表現を使わない。
誰が見てもわかるように書きましょう。
土地・建物・預金など、誰に何をどれだけあげるのかを明確にしましょう。
・遺言を作成した日付、自分の名前を必ず記入し、押印する
(実印でなくても良いが、実印が好ましい)
名前の記載は、芸名でもニックネームでも大丈夫??
日付の記載は、平成21年9月末日でも大丈夫??
無効にならない自筆証書遺言を作成したいのであれば、
自筆証書遺言作成後に専門家に添削してもらいましょう。
せっかく遺言書を書いたのに無効になってしまったら意味がありませんよね?
次回は自筆証書遺言より安心・確実な公正証書遺言について紹介していきたい
と思います。
【相続が争続に…!(事例)】
- 2009年9月16日(水) 23:52 JST
-
- 投稿者:
- 古家 秀樹
-
- 閲覧数
- 3,795
【相続が争続に…!(事例)】
最近、相談を受けた事例です。
その家族は、5人家族でここ2年の間に両親が亡くなりました。
残った財産と言えば、両親が住んでいたマンションだけ。
このマンションをどうするかで、兄弟間で揉めています。
第三者から見ると、マンションを売却して、そのお金を兄弟で
均等に分ければいいと思いますが、すんなりとはいきません…。
肉親には肉親なりの感情や思いがあるので、そう簡単には
いかないようです。
結局、家庭裁判所での調停をすることに決めたそうですが、
それが不調に終わると、裁判になります。
家族でそのようなことは避けたい、と最後まで言っていましたが、
話し合いができなければ、第三者に入ってもらい法的なアドバイスを
受けるのがよいのでしょうね。
兄弟の一人は、「お父さんが遺言を残しておいてくれたら…。」と
言っていました。
やはり、争いを避けるためには、遺言書を書いておくのが賢明な
方法であるとつくづく感じました。
最近、相談を受けた事例です。
その家族は、5人家族でここ2年の間に両親が亡くなりました。
残った財産と言えば、両親が住んでいたマンションだけ。
このマンションをどうするかで、兄弟間で揉めています。
第三者から見ると、マンションを売却して、そのお金を兄弟で
均等に分ければいいと思いますが、すんなりとはいきません…。
肉親には肉親なりの感情や思いがあるので、そう簡単には
いかないようです。
結局、家庭裁判所での調停をすることに決めたそうですが、
それが不調に終わると、裁判になります。
家族でそのようなことは避けたい、と最後まで言っていましたが、
話し合いができなければ、第三者に入ってもらい法的なアドバイスを
受けるのがよいのでしょうね。
兄弟の一人は、「お父さんが遺言を残しておいてくれたら…。」と
言っていました。
やはり、争いを避けるためには、遺言書を書いておくのが賢明な
方法であるとつくづく感じました。
~第1章~ できるだけ迷惑をかけない最期の迎え方
- 2009年9月 1日(火) 21:56 JST
-
- 投稿者:
- 古家 秀樹
-
- 閲覧数
- 3,366
大切なご家族に迷惑をかけずに最期を迎えたい、という
のは多くの方の共通した望みです。
しかし亡くなった後は必ず誰かにお世話にならないといけ
ません。
その時、残されたご家族にできるだけ迷惑をかけないよう
にするためには何をしておくべきでしょうか?
最近、書店で「エンディングノート」といわれる書籍を見かけ
ることがあります。
これはご自身が最期を迎えられた後でご家族が諸手続を
する際に、できるだけ困らないようにするためにご自身が事
前に作成しておくノートです。
財産の一覧表、出生から現在までの家族構成、加入して
いる保険など、死後の諸手続に必要な情報を記しておくノー
トです。
私には財産がないから関係ないわ、と思われる方もいらっ
しゃるかもしれませんが、相続税がかかるほどの財産がなく
ても、亡くなった後にはお葬式の準備、銀行口座の解約、生
命保険の手続など、多くの方に発生する様々な手続があり
ます。
大切なご家族が深い悲しみを抱えながら手続を行うわけで
すから、少しでもご家族の負担を軽くするために、ご自身の人
生を振り返って記録を残されることをお薦めいたします。
書店でエンディングノートを購入するのはちょっと・・・という
方のために、次回は何を書き残しておくと良いのかについて
のお話をしようと思います。
のは多くの方の共通した望みです。
しかし亡くなった後は必ず誰かにお世話にならないといけ
ません。
その時、残されたご家族にできるだけ迷惑をかけないよう
にするためには何をしておくべきでしょうか?
最近、書店で「エンディングノート」といわれる書籍を見かけ
ることがあります。
これはご自身が最期を迎えられた後でご家族が諸手続を
する際に、できるだけ困らないようにするためにご自身が事
前に作成しておくノートです。
財産の一覧表、出生から現在までの家族構成、加入して
いる保険など、死後の諸手続に必要な情報を記しておくノー
トです。
私には財産がないから関係ないわ、と思われる方もいらっ
しゃるかもしれませんが、相続税がかかるほどの財産がなく
ても、亡くなった後にはお葬式の準備、銀行口座の解約、生
命保険の手続など、多くの方に発生する様々な手続があり
ます。
大切なご家族が深い悲しみを抱えながら手続を行うわけで
すから、少しでもご家族の負担を軽くするために、ご自身の人
生を振り返って記録を残されることをお薦めいたします。
書店でエンディングノートを購入するのはちょっと・・・という
方のために、次回は何を書き残しておくと良いのかについて
のお話をしようと思います。
遺言書とは?
- 2009年8月12日(水) 13:40 JST
-
- 投稿者:
- 古家 秀樹
-
- 閲覧数
- 2,924
遺言書について その1
人が亡くなると相続が開始されますが、
お金が絡むことなので揉めてしまうことも多いです。
そのような相続争いを事前に防ぐ為に遺言書を残しておくという方法はとても有効です。
それだけではなく、
相続人の一人だけに、または、他の相続人より多く遺産を相続させたり、
時には、相続人以外の人に遺産を残すことも可能になります。
私の家族は、財産ないから関係ない?と思っていませんか?
私もビックリですが、
意外に、財産が少ない人程(1,000万円以内)大変よくトラブルになります。
特に遺言書を作成しておく必要が高いケースは、
子供達が相続でもめる可能性がある場合、
再婚している場合、子供のいない夫婦、愛人との間に子供がいる場合、
内縁の妻、相続人がいない場合などといわれています。
皆さんはきちんと「遺言書」を作成していますか?
遺言書は主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
「自筆証書遺言」は誰でも簡単に作成できる自分で書いて作成する遺言書ですが、
その反面、必要事項(必ず記載する必要のあること)を記入し忘れる等、色々と問題
になってしまうケースも多々あります。
「公正証書遺言」は公証人という方が公証役場と言われる場所にいてそこで作成し、第三者的な立場な方と一緒になって作成するので、上記の自筆証書遺言と比較すると問題も少なく確実な方法と言われておりますが、自筆証書遺言に比べると手間とお金がかかります。
「秘密証書遺言」は誰にも遺言の内容を知られたくない場合に利用されます。
次回は自筆証書遺言について、もう少し詳しく紹介していきたいと思います。
人が亡くなると相続が開始されますが、
お金が絡むことなので揉めてしまうことも多いです。
そのような相続争いを事前に防ぐ為に遺言書を残しておくという方法はとても有効です。
それだけではなく、
相続人の一人だけに、または、他の相続人より多く遺産を相続させたり、
時には、相続人以外の人に遺産を残すことも可能になります。
私の家族は、財産ないから関係ない?と思っていませんか?
私もビックリですが、
意外に、財産が少ない人程(1,000万円以内)大変よくトラブルになります。
特に遺言書を作成しておく必要が高いケースは、
子供達が相続でもめる可能性がある場合、
再婚している場合、子供のいない夫婦、愛人との間に子供がいる場合、
内縁の妻、相続人がいない場合などといわれています。
皆さんはきちんと「遺言書」を作成していますか?
遺言書は主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
「自筆証書遺言」は誰でも簡単に作成できる自分で書いて作成する遺言書ですが、
その反面、必要事項(必ず記載する必要のあること)を記入し忘れる等、色々と問題
になってしまうケースも多々あります。
「公正証書遺言」は公証人という方が公証役場と言われる場所にいてそこで作成し、第三者的な立場な方と一緒になって作成するので、上記の自筆証書遺言と比較すると問題も少なく確実な方法と言われておりますが、自筆証書遺言に比べると手間とお金がかかります。
「秘密証書遺言」は誰にも遺言の内容を知られたくない場合に利用されます。
次回は自筆証書遺言について、もう少し詳しく紹介していきたいと思います。
相続 第二弾 どれだけもらえる?
- 2009年8月11日(火) 01:46 JST
-
- 投稿者:
- 古家 秀樹
-
- 閲覧数
- 3,041
前回、残された者のうち誰が相続人になるか、というお話をしました。
その続きで、今回はこのようなケースです。
例)
被相続人(今回亡くなった人) 夫A
Aの妻 妻B
Aの子 子C
Aの前妻 前妻D
Aと前妻Dとの間に生まれた子 子E
Aの愛人 愛人F
Aと愛人Fとの間に生まれた子 子G(認知済み)
さて、夫Aの遺産が1,000万円あったとして、誰がどれだけ相続できるのでしょう?
答えは、
妻B 500万円
子C 200万円
子E 200万円
子G 100万円
です。
前妻Dは既に婚姻関係にないので相続人になれませんが、子Eは嫡出子(婚姻関係のもと生まれた子)なので、OK。
愛人Fは当然相続人になれません。問題は子Gです。もし認知をしていなかったら、原則、法律に定まった相続人にはなれませんが、今回のケースは認知をしているので相続人になることができます。
ただし、非嫡出子(婚姻関係にない2人の間に生まれた子)であるので、相続分は嫡出子の2分の1となります。
ちなみに、養子の場合は実子と同じ相続分となりますので、もし愛人Fの子Gにも実子と同じ相続分を、と思うのなら養子縁組をすればOKです。
その続きで、今回はこのようなケースです。
例)
被相続人(今回亡くなった人) 夫A
Aの妻 妻B
Aの子 子C
Aの前妻 前妻D
Aと前妻Dとの間に生まれた子 子E
Aの愛人 愛人F
Aと愛人Fとの間に生まれた子 子G(認知済み)
さて、夫Aの遺産が1,000万円あったとして、誰がどれだけ相続できるのでしょう?
答えは、
妻B 500万円
子C 200万円
子E 200万円
子G 100万円
です。
前妻Dは既に婚姻関係にないので相続人になれませんが、子Eは嫡出子(婚姻関係のもと生まれた子)なので、OK。
愛人Fは当然相続人になれません。問題は子Gです。もし認知をしていなかったら、原則、法律に定まった相続人にはなれませんが、今回のケースは認知をしているので相続人になることができます。
ただし、非嫡出子(婚姻関係にない2人の間に生まれた子)であるので、相続分は嫡出子の2分の1となります。
ちなみに、養子の場合は実子と同じ相続分となりますので、もし愛人Fの子Gにも実子と同じ相続分を、と思うのなら養子縁組をすればOKです。
相続人になれる人なれない人
- 2009年7月20日(月) 02:21 JST
-
- 投稿者:
- 古家 秀樹
-
- 閲覧数
- 4,370
「相続」とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人が引き継ぐことです。
では、相続人になれる人なれない人の範囲はどこからどこまでか、ご存知ですか?
(遺言書がない場合)
まず、被相続人の配偶者(夫・妻)は無条件で相続人となります。
そして次からは順位があり、先順位の人がいると後順位の人は相続人にはなれません。
第一順位 子
第二順位 親
第三順位 兄弟姉妹
それでは、残された方々が次のような場合は誰が相続人となるのでしょうか。
例) 遺言書がない場合
被相続人 夫A
夫Aより先に死亡の妻 妻B(死亡)
Aより先に死亡のAの子 子C(死亡)
Cの子(Aの孫) 孫D
Aの父 父E
Aの母 母F
答えは、孫Dです。
第一順位の「子C」がいないため、第二順位の「親EF」である父E母Fが相続人になるかと思いきや、「孫D」は「代襲相続(たいしゅうそうぞく)」という制度によって、先に亡くなった「子C」の代わりに相続人になるのです(子→孫→曾孫…、と続く)。
ここで、孫Dを中心に相続トラブルが起きることも多々あり得ます。
未然に防ぎましょう。あなたのお孫さんのために。
次回は、また少し複雑な相続人について、書きたいと思います。