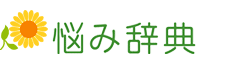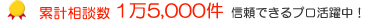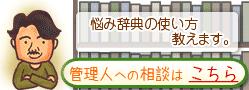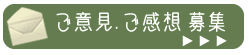犬のストレスあれとこれ
- 2010年2月 1日(月) 18:30 JST
-
- 投稿者:
- 渋谷 宥葵
-
- 閲覧数
- 7,279
今日は、そもそもこの「ストレス」とはいったい何ぞや!?をテーマにしたいと思います。
簡単に言うと、ストレスとはストレッサーという刺激があり、このストレッサーによってストレス反応を引き起こします。
ストレッサーはどんなものがあるんでしょうか?
・物理的ストレッサー
(外界刺激からの刺激。タオルや服の感触や騒音、暑い寒いなど)
・生理的ストレッサー
(身体の痛み、炎症や風邪など、身体的に感じること)
・心理的ストレッサー
(怒りや不安、興奮など)
そして
ストレスには大きく分けて2種類あります。
・いいストレス
・悪いストレス
いいストレスとは人間でたとえると結婚式や楽しい旅行の前の緊張などです。犬でいうと、飼い主がフリスビーを投げてくれる前やご飯を前に飼い主の「食べて良いよ!」のサインを待っている状態。武者震いというものそうですね。
悪いストレスというのは精神的肉体的に苦痛や不安に感じるものがそうです。
瞬間的にすごくいいストレッサーでも、それが長引くといや~な気分になり悪いストレスにつながることがあります。 なにごとにも、「いい塩梅」が大切ですね。
ストレスは全部が悪いものではありません。
自己成長のためにもストレスを感じることはとても大切です。
では、何がいけないのか?文字通り「悪いストレス」がくせ者。
犬も人もストレッサーを完全に取り除いて生きることは到底不可能です。
そこの中で何が問題かというと、ストレスを長期にわたって感じ続けていることです。
これらが身体の調子を狂わせ、分離不安などの心理的問題を引き起こし、
犬の問題行動の原因になりうるのです!
犬のストレッサーとして考えられるのは
・欲求(または本能)が満たされない。
・飼い主から愛情がもらえない
・怪我や痛み、身体の不快感
が大きく上げられます。
遊びたいのに遊べない。食べ物が欲しい。うるさくて眠れない!
など原因はさまざま。人間にとっては「これこれこういう事情だから仕方がない」と思いがちですが、犬には人間の事情はわかりません。
そして、こういったストレスがかかり続けると、犬の行動にも変化が現れます。
・無駄吠えする
・むやみに身体のどこかを引っかく
・同じ行動をずっとする
・過剰に甘える
・わざと失敗する
・食欲がなくなる
・攻撃的になる
人間にもそんなことがありますよね?イライラしたり、ずっとタバコを吸い続けたり、爪を噛んだり、食欲がなくなる。犬もまた習性は違えども、人
間と同じ生き物です。つらいときは必ず人間にもキャッチできるサインが発せられています。
ストレスの原因を取り除くのが一番ですが、それが出来ないときは、人間がジェットコースターで大声を出して嫌な気分を発散するように、犬も外で思いっきり遊ばせてあげましょう。
そして、なにより飼い主の愛情を十分に注いであげましょう!
ストレス解消のキーは「愛情」にあります。
つらいときそっと背中を撫でて抱きしめてくれた手の暖かさ。
「愛されてる」「必要とされている」と感じる安堵感と充足感。
あなたもきっとそんな経験があるのではないでしょうか?
///////////////////////////////////////////////
Fys with Dogs
メールマガジンの登録はこちらから
http://www.melma.com/backnumber_184061/
ミクシィはこちら
http://mixi.jp/show_profile.pl?id=5268190
ミクシィのコミュはこちら
http://mixi.jp/view_community.pl?id=4646457
新しいペットでグリーフは癒せるか?
- 2009年10月16日(金) 20:24 JST
-
- 投稿者:
- 渋谷 宥葵
-
- 閲覧数
- 2,444
ペットを亡くしたばかりの人に新しいペットを迎えるように薦める。
昔からとてもよくあることです。
それは「新しいペットが、きっとその人の悲しみを癒してくれる」という希望が含まれているからです。
確かに動物のもたらす癒し効果は、何十回のカウンセリングに勝ることがあります。
愛するペットを亡くした時に感じる心の穴を埋めるために、新しいペットを求めるのは自然のことだと思います。
しかし、その心の穴が、まるでクッキーの型のように決められた形だったらどうでしょう?新しいペットを無理矢理中に押し込めることになります。
ペットを失ったらすぐに新しいペットを飼わないといけない。そういうわけではないのです。
ある60代の女性がいます。彼女は5ヶ月前に愛犬リリー(シーズー)を13歳で亡くし、周囲に薦められるままに新しい犬(トイプードル)を飼いました。
一見その犬を大事に大事に育てているようですが、しかし、お散歩仲間、ペットショップの店員はあることに気がつきました。
彼女は良くこんな話をします。
「この子はまだお座りが出来ないの。リリーはこの(歳)くらいにはフセも出来たのに」
「この子は好き嫌いが激しいの。リリーは何でも良く食べたのに・・・」
「きっとこの子はリリーの生まれ変わりだと思うの。寝方がリリーそっくり」
など、事あるごとにリリーを引き合いに出します。まるで、今の犬と比べていかにリリーが優秀で最高のパートナーだったかを自慢しているように感じますね。その反面新しい犬をリリーの「生まれ変わり」だと主張しています。それは、新しい犬をリリーの生まれ変わりと思わないと愛せないかのようです。そして少しでもリリーと今の犬の共通点を見つけ出し、そこに安心している。
そうです。自分の心に空いた型に、無理矢理新しい犬をぎゅうぎゅう押し込めています。押し込むことが出来ないと、やっぱりリリーのほうが優秀だったと思い、益々リリーへの愛着を強くしています。
彼女はリリーとの別れの時に感じた、グリーフ(悲観)としっかり向き合えていなかったのです。
いや、むしろ向き合う時間がなかった。と言うほうが正しいのかもしれません。
リリーが亡くなった事実が、新しい犬を飼うことによって、実感できなかった例です。
新しいペットを迎える前に、新しいペットを薦める前に、考えましょう。
あなた自身の感情
・しっかりとグリーフに向き合えたか。また、前の犬の死を受け入れているか。
・前の犬に対しての罪悪感を(持っているなら)解決しているか。
・新しい犬を飼いたいと思う理由は何か?
・新しい犬にすべての問題(の解決)を丸投げしていないか?
・あなた自身が新しい犬を飼うことを望んでいるか?
ライフスタイル(新しい犬を飼うことが出来る生活をしているか?)
犬を飼うことに対しての能力(年齢や金銭面、環境など)
新しい犬を飼うことは、たくさんの期待とたくさんの不安が伴います。
しかし、上記の条件をクリアしたとき、「ああ、また新しい絆を作りたい。新しい犬を迎えたい」と思うのは当然の心理なのです。
「新しいペットでグリーフは癒せるか?」
皆さんはどう思われましたか?
カウンセリングってなに?
- 2009年10月16日(金) 20:11 JST
-
- 投稿者:
- 渋谷 宥葵
-
- 閲覧数
- 2,446
「カウンセリングって?」
と聞かれたら、
「怖い」
「病気の人が行くの?」
「私には関係ない」
「行くのが恥ずかしい」
という答えが多いです。
「違います!そんな恐ろしいものでも病的なものでもまったくなく、むしろノンクリニカル(健常)な人こそ受けて欲しいものなんです!」
と訴えても、なかなか浸透しないというのは、カウンセラーとしては悲しい現実です・・・。
今日は「カウンセラーとは何?」を書いていきたいと思います。
***
「カウンセリングって?」
ウィキペディアには『何らかの問題を抱えている人から相談を受け、それに適切な援助を与える職種』と書いてあります。
この「何らかの問題」=「心の病」と直結して考える方が、多いのではないでしょうか?
そもそも、カウンセラーという国家資格は存在しません。
え?じゃあ、臨床心理士って?精神科って?心療内科って~~??
そんな疑問を、今日はまるっと解決出来るよう記事を書いていきたいと思います。
時々看板で
『渋谷クリニック 心療内科』
や
『ピノコ病院 精神科』
などと書かれているものを、目にすることがありますね。
「え~、どっちも同じでしょう~」
と思われるかもしれませんが、ぜんぜん違います。
または
「私は精神科に行くほどじゃないから、心療内科にする」
という人もいるかもしれません。
まずこの誤解を解きましょう!
「心療内科」は「精神科」の軽度ヴァージョンではありません。
畑がまったく違うのです。
精神科→精神疾患に関する医師。薬を処方できる。うつや統合失調症、心身症や不眠症。さまざまな精神疾患を受け付けている。重度の精神病患者などための入院施設もある。
心療内科→内科学から分野分けになった。おもに身体(内科)を診る。心身医学。心身症は身体の不調の訴えが主です。いわば、内科のお医者さん。ストレスから身体の調子がおかしくなった。というときはこちら。
神経内科→脳神経の疾患を取り扱う。ドーパミンとかセロトニンとか。
よくわからないですね。
つまり、
身体の不調がメインの訴えならば、内科か心療内科。
心の症状がメインの訴えならば、精神科。
となります。
さて、つづき。
臨床心理士→文部科学省所轄の財団法人の認定資格。スクールカウンセラー事業を行う。精神科とタッグを組む場合もあり、臨床心心理士がカウンセリング、精神科医が薬物などの処方。およびそれによる治療をする。
産業カウンセラー→社団法人日本産業カウンセラー協会認定資格。働く人たちの問題を、解決できるように援助する。
※主な使用療法は来談者中心療法
セラピスト→○○セラピストなど、いろんなところで聞いたことがあるかもしれません。セラピーは療法。各種心理療法を行う者です。
※心理療法(大きく分けて精神分析/行動療法/来談者中心療法があげられる)
※カウンセラーがよくカウンセリングに使用する。
※人によって、「この療法はあわないわ~」という場合もあります。
※アロマテラピーのテラピーと同義。
コンサルタント→相談役。情報を提供したりアドバイスをする。クライアントの力で問題を解決できるよう、さまざまな角度から協力する。
アナリスト→データに基づき分析する。分析家
心理カウンセラー→相談員。傾聴をメインに心をサポートする。クライアントが自分の力で問題を解決できるようにサポートする。アドバイス、情報提供はない。
※各種心理療法を使用
近所のおばちゃん→時々ありがたいけど、どきどきおせっかいで的外れ?
いろいろ相談を受け付ける窓口がありますね。
これらすべてがごちゃごちゃになり、カウンセリングとリンクさせてしまうから、
カウンセリング・・・病気・・・病院・・・大変!
という意識が生まれてしまうんです。
そもそも、カウンセリングというのはクリニカル(治療必要)な人たちだけが行くものではありません。
カウンセリング=クリニカル ではないのです。
***
アメリカ人やイギリス人は、カウンセラーをとてもよく使い分けます。
個人の問題にはこのカウンセラー
夫婦の問題はこのカウンセラー
子供はこのカウンセラー
など、1人が、何人ものカウンセラーの名刺を持っています。
そうです。
カウンセリングの大きな役割とは、
ノンクリニカル(健常)者が、いかにうまく人間関係や自分のストレスを解決するかを、
第3者のプロ(カウンセラー)に手伝ってもらい、
自ら方向性を見つけるものなのです。
ノンクリニカルのときにこそ、カウンセリングを大いに利用するためのものであり、
我慢して我慢して、クリニカルになって、
ようやっとカウンセリングを受けられる。ということではないのです。
誤解の多い日本。
カウンセラーたちは、気軽に皆さんが尋ねてこれるように、カウンセラーの印象をよくするようにいろいろ考えています。
どうか、カウンセラー・カウンセリングの偏見をなくし、
日頃から明るく生きていられるように、心のチューニングに気軽にご利用してください。