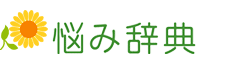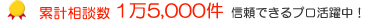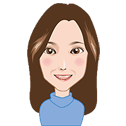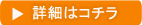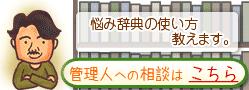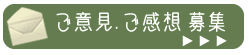相談&回答 |
約9分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間 |
回答プロ: 水時 功二

父の車の鍵を返してもらえません。また、賃貸保証人の地位は承継するのでしょうか? 〜 続き
ご相談者:30代/女性
先日父の車の件と保証人で返答をいただいたものです。
わかりやすい説明をどうもありがとうございました。
いただいた返答に関しまして、再度質問させていただいてもよろしいでしょうか???
「保障人に関しては、たとえば賃貸借契約が2年契約であれば、更新時に保証人(相続による承継人)として、署名をしなければいいと思います。ただ、ご心配であれば、相続財産がない場合、相続放棄をすれば問題ありません。」
と返答をいただきましたが、賃貸契約については更新時に再度保証人の確認を取らない不動産会社もあると思います。
現に私が今借りている借家も更新時に「保証人の変更さえなければ、再度保証人の署名や印鑑はいらない」と言われました。
となりますと知らないうちに、また父が保証人として更新されてしまうケースもあると思うのです。
相続財産がありますので放棄は出来ませんし、どうしてもこの賃貸契約の保証人を変更したいのですが、
何か方法はございますでしょうか。
また、こちらをもっと詳しく知りたい場合、どなたに相談すべき問題なのでしょうか?(弁護士、司法書士など)
また、父が連帯保証人になっているかどうか確認する手段として、以下を教えていただきありがとうございました。
■クレジットカード関係
(株)シー・アイ・シー(CIC)
■消費者金融関係
全国信用情報センター連合会(全情連)
■上記以外(銀行など)
全国銀行個人信用情報センター
早速こちら全てに連絡をとって、書類が揃い次第情報の開示を求める予定です。
しかし、全国銀行個人信用情報センターに関しましては、
「本人からの銀行からの借り入れの有無」 は調べられるが、
「第三者が銀行から借り入れをした時連帯保証人になったかどうか」 は調べられないといわれました。
どうしたら保証人関連を洗いざらし全部調べることが出来るのでしょうか?
出来れば、どなたか(弁護士、司法書士、調査会社など)にお願いして調べてもらいたいのですが、
どなたに相談すべき案件なのでしょうか?
たびたびの質問を申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
30代/女性 | 日付:2008年3月10日(月) 15:29 JST | 閲覧件数: 1,919
詳しくお知りになりたい場合、お近くの司法書士会等に紹介をお願いしてみてください。
確かに賃貸借契約の保証人に関しては、特段の事情がない限り、保証契約も更新されるとした判例はございますが、それは原則であって、更新できない「一定要件」もございますので、保証人の確認と取らない不動産会社の言い分が必ずしも通るという訳ではありません。
そもそも、こういう過去の争いの結果、出された判例をもとに、再度の保証人の署名や印鑑は要らないと言っているのかもしれませんが、判例にはそれぞれ、細かい事例分析が必要であり、すべての事例に関して当てはめるという危険な扱いはやめたほうがいいと思います。
そういう意味で、保証契約に関しても、引き続きその意思があるのかどうか(保証人からしてみれば、2年契約だから最初は署名したのであって、もし永久に保証しろと言われた場合、署名したのでしょうか?こういうところから攻めれば、もしかしたら別の判決が出される可能性も否定できません。)、不動産会社はその都度、確認の義務があるはずです。
念のため、最後尾に判例を記載しておきます。
今回のケースは、賃貸人と友人Aさんを入れて、保証契約の見直しを交渉してみるのはいかがですか。相続人だからといって、お父様の死後は関係なくなる、友人Aさんの賃貸保証をするのは、常識ではおかしな話だから、そこを、賃貸人に主張し、保証人の変更を申し出てみてください。
しかし、法律上は、保証人の地位は、相続人に承継されるということは、認識しておいてください。
もし、どなたか専門家をお願いしたいのであれば、お近くの司法書士を紹介してもらい、面談相談を申し込むといいでしょう。http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/index.html
また、情報センターへの開示請求は、連帯保証人の相続人として「強く」請求してください。その際、戸籍の提示等を求められるかもしれませんが。。。あとは、交渉しだいです。もし不可能ならば、やはり専門家に頼んでみてください。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
【 事例 】
借家人の債務を保証した者(保証人)が借家契約の更新後も保証人としての責任を免れないとされた事例である。(最高裁平成九年十一月十三日判決 判例タイムズ九六九号一二六頁)
【 事件の概要 】
X:原告(個人、Aの保証人)
Y:被告(賃貸人)
(関係人)
A:Xの実弟(賃借人)
Yは、昭和60年5月31日にXの実弟であるAに兵庫県内のマンションを賃貸した。賃貸借契約においては、期間が同年6月から2年間、賃料が月額26万円と定められた。その際、XはYに対し、Aが賃貸借契約に基づいて負担するすべての債務について連帯して保証することとなった。
YとAとの間の賃貸借契約においては、期間の定めに加えて「但し、必要あれば当事者合議の上、本契約を更新することも出来る」と規定されていた。Yは、賃貸借期間を家賃の更新期間と考えており、期間満了後も賃貸借関係を続けられることを予定していた。また、Xのほうは、保証契約締結当時にAが食品流通関係の仕事をしていて高額の収入があると認識していたことから、Aの支払い能力は心配していなかった。
AとYとの間の賃貸借契約は、3回にわたり更新された。すなわち、まず昭和62年6月ころ、期間を同年6月から2年間と定めて更新する旨が合意され、ついで平成元年8月に、期間を同年6月から2年間、賃料を月額31万円と定めて更新する旨が合意され、そして平成3年7月に、期間を同年6月から2年間、賃料を月額33万円と定めて更新する旨が合意された。
各回の更新の際に作成された契約書の連帯保証人欄には「前回に同じ」と記載されているにとどまり、Xによる署名押印がされていない。また、各更新の際にYからXに対してAの保証を続ける意思を確認する問い合わせがなされたことはなく、XがAに対して引き続き連帯保証人となることを明示して了承したこともなかった。
Aは、2回目の合意更新による期間中の賃料のうちの75万円と3回目の合意更新による期間中の賃料など759万円を支払わなかった。Yは、平成4年の7月中旬ころ、Aに対し賃貸借契約の更新を拒絶する旨を通知すると共に、平成5年6月に賃料不払いが続いている旨をXに連絡した。Aは、同月Yに対しマンションを明け渡した。
このような経過の後、XがYに対して保証人としての責任がないことを主張したのがこの事件の概要である。
【 理由 】
建物の賃貸借は、一時使用のための賃貸借等の場合を除き、期間の定めの有無に関わらず、本来相当の長期間にわたる存続が予定された継続的な契約関係であり、期間の定めのある建物の賃貸借においても、賃貸人は自ら建物を使用する必要があるなどの正当事由を具備しなければ、更新を拒絶することができず、賃借人が望む限り、更新により賃貸借関係を継続するのが通常であって、賃借人のために保証人となろうとする者にとっても、右のような賃貸借関係の継続は当然予測できるところであり、また保証における主たる債務が定期的かつ金額の確定した賃料債務を中心とするものであって、保証人が予期しないような保証責任が一挙に発生するようなことはない。
期間の定めのある建物の賃貸借において、賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当であり、保証人は、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れないというべきである。
【 解説 】
保証人の責任は、保証契約に基づいて生ずるものであり、この保証契約は、保証人になろうとする者と債権者との間で結ばれる。この事件の保証契約は、賃借人が賃料などを支払わない場合には、保証人が不払いの債務を弁済する趣旨のものである。
銀行からの借り入れなどと異なり、賃料債務は一定期間ごとに定まった額で発生するものであるから、債務額の予測が容易であり、また建物の賃貸借は更新がなされることが少なくない。これらのことを考えると、この事件の判決が保証人の責任は更新後も残ると考えていることが原則であるとし、そのように考えたとしても保証人にとって過酷ではないとするところも一応理解することが出来る。
しかし、事例によっては長期に賃料滞納が続くなどして保証人の責任が予想外に大きくなり、保証人にとって過酷となることもなくはない。大審院の判例(後掲参考判例(1))においても、一定の要件の下に、保証人が将来に向けて保証契約を解除することを認めたものがある。
一定の要件とは、(1)保証期間の定めがないこと、(2)保証契約締結後相当の期間を経過したこと、(3)賃借人がしばしば賃料の支払いを怠り将来も誠実にその債務を履行する見込みがないか、あるいは、保証後賃借人の資産状態が著しく悪化し、それ以上保証を継続するとその後の分に対し将来求償権の実現がおぼつかなくなるおそれがあるか、もしくは、賃借人が継続して債務の履行を怠っているのに賃貸人が保証人にその事実を告知せず、また、遅滞の生ずるごとに保証債務の履行を求めず突如として一時に多額の延滞賃料の支払いを求め保証人を予期せぬ困惑に陥らしめる等の事態が生じたこと、(4)それにも関わらず賃貸人が賃貸借の解除、明渡請求等の処置を取ることなく依然として賃借人に使用収益をさせていること、である(副田隆重・判例タイムズ九八二号五七頁)。
また、保証契約の解除を認めるところまではいかなくても、ある金額を超えた部分については保証人の責任が及ばないとする保証責任の限定を認めた裁判例もみられる(後掲参考判例(2))。
この事件の判決それ自体も、一般論としては、特別の事情がある場合に保証人に対する責任の追及が信義に反することとなる場合があることを認め、ただし、本件事件の具体的な処理においては、これを認めなかった。更新の経過などに鑑みれば、保証人の損害を回避すべき義務が賃貸人にあったとみる余地もあると思われる。
【 参考判例 】
(1)大審院 昭和八年四月六日 判決 民集一二巻七九一頁
(2)東京地裁 昭和五十一年七月十六日 判決 判例時報八五三号七〇頁
回答日時:2008年3月16日(日) 14:29 JSTお礼のコメントを書く
・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。
こちらのプロも相談受付中です。
悩み辞典は、安心して登録・相談できます。
※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。
※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。
※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。
※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。
※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。