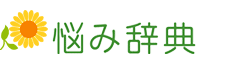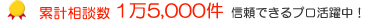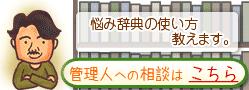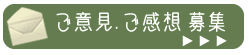自己表現力の向上
- 2010年2月 7日(日) 10:22 JST
-
- 投稿者:
- ゲストユーザー
-
- 閲覧数
- 4,497
日本の学生は、ひいき目に見ても自己表現力が弱い。
「質問がないか」
と聞くと
「ない」 と答えるのが日本
有りすぎて困るのがアメリカとインド
韓国・中国も良く質問がある。
グローバル化が着実に深化していく中、自己表現力が弱い学生は
圧倒的に不利。
自分の言葉で、自分の存在をしっかりとアピールできる能力が必要。
(2月5日(金)読売新聞 新潟県立大学長 猪口 孝氏)
________________________________
学生カウンセリングの現場で、エントリーシートの書き方が苦手、
と言う学生の言葉が、上記のコメントと妙にリンクした。
グローバル化の潮流の一部が、何か統一化という一般化的な保守的な
淀みを作っているような、そんな気にもなる。
「赤信号、皆で渡れば怖くない」 みたいなものだろうか。
日本人は、特にこのような質が強い民族でもあるようだが・・・
いわゆる一般常識といわれるような物の見方(それ自体どうか?)では、
一種独特ではあるが、多少なりとも市民権を得てきている「アキバ系」
のようなカラーも、ひょっとしたら自己表現力に長けた人達なのかも
しれませんね。
新たな思考の入り口が見えてくる!?
- 2010年2月 4日(木) 10:24 JST
-
- 投稿者:
- ゲストユーザー
-
- 閲覧数
- 3,758
今朝、1時間のウォーキングをしてみました。
といっても、単に運動が目的ではなく、自宅からある施設までの時間を計るためでした。
普段、最寄駅までの15分より、少し多いぐらいかと簡単に考えていたのですが、
なんと、ほぼ倍の30分かかってしまいました。
途中で 「引き返そうかな・・」 なんて頭をよぎったのですが、計るという目的を
果たすために、甘い誘惑を振り切り目的地まで辿り着きました。
その時点で体はもうポカポカで、なんとなく吐息が白く濃い感じ。。
「30分か~」 と思いながら、すぐさま引き返して帰宅。
往復1時間のウォーキングで、足腰に筋肉疲労は隠せませんが、有酸素運動に
なったのか、いつになく頭がサッパリしている感じです。
寝起きで、モヤモヤ~との意識で机に向かうのとでは、相当の違いがあります。
それは、抱えている課題や、義務感みたいなものに囚われた意識が無いということです。
1日24時間は皆同じ、不公平ないことですから、その限定の中で自分がやれる形で
着実にこなしていく、それしかできないんだ、と思えることがとても健全に思えます。
「行動を変えれば、考えも変わる」
とはよく言われることですが、それと同時に
「行動すれば、考えを変える準備ができる!」
と感じた朝でした。
5分、10分でも体を動かすことで、違った方向の入り口が見えてくるのでは
ないでしょうか!
といっても、単に運動が目的ではなく、自宅からある施設までの時間を計るためでした。
普段、最寄駅までの15分より、少し多いぐらいかと簡単に考えていたのですが、
なんと、ほぼ倍の30分かかってしまいました。
途中で 「引き返そうかな・・」 なんて頭をよぎったのですが、計るという目的を
果たすために、甘い誘惑を振り切り目的地まで辿り着きました。
その時点で体はもうポカポカで、なんとなく吐息が白く濃い感じ。。
「30分か~」 と思いながら、すぐさま引き返して帰宅。
往復1時間のウォーキングで、足腰に筋肉疲労は隠せませんが、有酸素運動に
なったのか、いつになく頭がサッパリしている感じです。
寝起きで、モヤモヤ~との意識で机に向かうのとでは、相当の違いがあります。
それは、抱えている課題や、義務感みたいなものに囚われた意識が無いということです。
1日24時間は皆同じ、不公平ないことですから、その限定の中で自分がやれる形で
着実にこなしていく、それしかできないんだ、と思えることがとても健全に思えます。
「行動を変えれば、考えも変わる」
とはよく言われることですが、それと同時に
「行動すれば、考えを変える準備ができる!」
と感じた朝でした。
5分、10分でも体を動かすことで、違った方向の入り口が見えてくるのでは
ないでしょうか!
毎日行う行動の積み重ね
- 2010年1月30日(土) 11:09 JST
-
- 投稿者:
- ゲストユーザー
-
- 閲覧数
- 3,939
毎日行う行動の積み重ねが、人間の生きがいである。
人間は、時々刻々どんな行動をするか問われている。
ゴロゴロ横になっている、テレビを見ている、意を決して掃除にとりかかる
怠け心を振り切って仕事をする・・・
人間は一時一時、どんな行動をするのかが問われている。
そして、プラスの価値をもった行動を選択し、その総和が生きがいにつながる。
(V・E・フランクル)
何もない、何もできない、解らない・・・・
という思いが頭にあれば、それだけで意識が渦巻いてしまう、
しかし、そんな中でも自分が動くことさえできれば、
何かが目に映り、
何かを五感で感じる。
そして、その感じたことにまた新たな思いが生まれ
そして行動につながる。
人間は、時々刻々どんな行動をするか問われている。
ゴロゴロ横になっている、テレビを見ている、意を決して掃除にとりかかる
怠け心を振り切って仕事をする・・・
人間は一時一時、どんな行動をするのかが問われている。
そして、プラスの価値をもった行動を選択し、その総和が生きがいにつながる。
(V・E・フランクル)
何もない、何もできない、解らない・・・・
という思いが頭にあれば、それだけで意識が渦巻いてしまう、
しかし、そんな中でも自分が動くことさえできれば、
何かが目に映り、
何かを五感で感じる。
そして、その感じたことにまた新たな思いが生まれ
そして行動につながる。
ピンチはチャンス
- 2010年1月18日(月) 14:29 JST
-
- 投稿者:
- ゲストユーザー
-
- 閲覧数
- 5,394
「ピンチ」は「チャンス」
よく聞かれるフレーズだと思いますが、まさに今の日本はそのピンチ状態です。
長いデフレによる経済のそこが続き、合わせて雇用情勢の悪化、進むリストラ。
大学生の内定率の低下。
そして最近では、大手航空会社の再建問題などなど、全てにおいてアゲインストの
強風が吹き荒れています。
ただ、そんな不況の中でも、ユニクロみたいに一人勝ちの企業が存在しているのも
また事実です。
違いはいったい何なのか?
____________
企業の経営は、換言すれば「個人の経営」つまり、自分をどのように活かして伸ばして
いくのか、とまったく同じである。
先行き真っ暗、道が見えない、さてどうしよう?
いつまでも道が見えてくるまでじっと待つのか、または自分で新しい道を作り出して
いくのか?
それが大きな分かれ道なのでしょう。
昨日の新聞に、ある人材ビジネスの女性社長の記事があり、その中のコメントをご紹介
しましょう。
「必要とされる人材になるには、その場にいないと始まらない。まずは社会に出て、
挑戦するチャンスをつかめばいい」
まさに 「ピンチはチャンス」 誰もしない暗闇で自分の道を作り出す。
これは、何も学生向けだけの意味でもなく、今どん底といわれる状況に臥している
社会人全員に当てはまる言葉だと思います。
よく聞かれるフレーズだと思いますが、まさに今の日本はそのピンチ状態です。
長いデフレによる経済のそこが続き、合わせて雇用情勢の悪化、進むリストラ。
大学生の内定率の低下。
そして最近では、大手航空会社の再建問題などなど、全てにおいてアゲインストの
強風が吹き荒れています。
ただ、そんな不況の中でも、ユニクロみたいに一人勝ちの企業が存在しているのも
また事実です。
違いはいったい何なのか?
____________
企業の経営は、換言すれば「個人の経営」つまり、自分をどのように活かして伸ばして
いくのか、とまったく同じである。
先行き真っ暗、道が見えない、さてどうしよう?
いつまでも道が見えてくるまでじっと待つのか、または自分で新しい道を作り出して
いくのか?
それが大きな分かれ道なのでしょう。
昨日の新聞に、ある人材ビジネスの女性社長の記事があり、その中のコメントをご紹介
しましょう。
「必要とされる人材になるには、その場にいないと始まらない。まずは社会に出て、
挑戦するチャンスをつかめばいい」
まさに 「ピンチはチャンス」 誰もしない暗闇で自分の道を作り出す。
これは、何も学生向けだけの意味でもなく、今どん底といわれる状況に臥している
社会人全員に当てはまる言葉だと思います。
「生きる力」不足
- 2010年1月 8日(金) 10:58 JST
-
- 投稿者:
- ゲストユーザー
-
- 閲覧数
- 3,936
一昨日の新聞記事より
とある企業で学生60人面接した中で、中学生レベルの計算問題ができない学生が多く、
不採用が続いた、と。
また、院卒の学生の点数が、高卒の中高年よりも低かった、との企業談話も。
「生きる力」(文科省)とは
基礎学力だけではなく、思考力、意欲、コミュニケーション
能力などの総合力である。
また、日本能率協会マネジメントセンター実施、企業人事担当者へのアンケートでは、
若手社員の問題点として
「読み書きなどの基本能力の低下」 53%
「主体性不足」 51%
「コミュニケーション能力不足」46%
だったとのこと。
ゆとり教育の誤った政策の産物というだけではなく、次世代、ひいては日本国そのもの
を展望する際、
「生きる力」=「活きる力」そして、「人間力」を育む
環境作りが重要
なのではないだろうか。
心理的サポートも兼ね備える、キャリアカウンセラー
の大きな役目でもあろうかと思う。
年の初めの勇気と感動
- 2010年1月 3日(日) 15:44 JST
-
- 投稿者:
- ゲストユーザー
-
- 閲覧数
- 2,756
今年も箱根駅伝で、いろいろなドラマが展開されました。
某大学の2連覇という結果にはなりましたが、場面の全てにおいて感動を覚え、そして学生たちの
その熱き想いに涙がとまりませんでした。
いつも見ていて感じるのですが、確かに学生スポーツであり、勝負も大事ですが母校のために
同じ思いを持ち、目的を一緒にして頑張る姿、そこがとても素晴らしいことだと。
そして、それは単に団体スポーツだから、と言うことだけではなく、団体として取り組む気持になれる
その精神だと思うのです。
昨今の個人主義的感覚や、優劣が明確な競争社会の中で生き抜く術しか覚えないような
そんな殺伐とした関わりではない、一緒に同じ目標に向かって努力する、そしてそれはお互いに
労り合い、互いに受容し合える関係性が、そこにあるから感動を与えてくれるのではないのか、
と思うのです。
簡単に言えば、助け合える仲間がいて、そして世界がある。
これが、本来日本人として持っている哲学・文化ではないのでしょうか!
悩み苦しんでいる時には、皆で共有して解決を求めていく。
グローバル社会と言われる、競争社会の中にあっても、このような日本人的哲学を持ち、
お互いを支え合えるような社会を、今一度作っていく必要があるのかもしれませんね!
某大学の2連覇という結果にはなりましたが、場面の全てにおいて感動を覚え、そして学生たちの
その熱き想いに涙がとまりませんでした。
いつも見ていて感じるのですが、確かに学生スポーツであり、勝負も大事ですが母校のために
同じ思いを持ち、目的を一緒にして頑張る姿、そこがとても素晴らしいことだと。
そして、それは単に団体スポーツだから、と言うことだけではなく、団体として取り組む気持になれる
その精神だと思うのです。
昨今の個人主義的感覚や、優劣が明確な競争社会の中で生き抜く術しか覚えないような
そんな殺伐とした関わりではない、一緒に同じ目標に向かって努力する、そしてそれはお互いに
労り合い、互いに受容し合える関係性が、そこにあるから感動を与えてくれるのではないのか、
と思うのです。
簡単に言えば、助け合える仲間がいて、そして世界がある。
これが、本来日本人として持っている哲学・文化ではないのでしょうか!
悩み苦しんでいる時には、皆で共有して解決を求めていく。
グローバル社会と言われる、競争社会の中にあっても、このような日本人的哲学を持ち、
お互いを支え合えるような社会を、今一度作っていく必要があるのかもしれませんね!
チョー優しい♪
- 2009年12月15日(火) 12:21 JST
-
- 投稿者:
- ゲストユーザー
-
- 閲覧数
- 3,233
「○○先輩って、優しいよね~♪」
「そうだよね、失敗しても、大丈夫だよ~って言ってくれるもんね♪」
「ホント、チョー優しいよね~♪」
今朝、電車の中の女子高生の会話です。
すぐ横に立っていたので、会話をそのまま聴くことができました。
聴いていると、なんだか微笑ましく思えてきて、ニヤッとなりそうなのを
抑えたぐらいです。
普段電車の中での会話では、なんかしらのグチだとか、誰かに対する
批判じみた言葉が多いように思われるので、今朝の彼女たちの会話
を聴いていて、とてもハッピーな気分にさせてもらいました。
プラスの言葉を出せば、出した本人も幸せだし、周りの人に対しても
きっと幸せを与えることができるのでしょうね♪
自己一致
- 2009年11月24日(火) 10:30 JST
-
- 投稿者:
- ゲストユーザー
-
- 閲覧数
- 3,903
◎「自己一致」
とは、今自分が体験していること、今実感していること
それが ”自分である” と感じることが、自分の概念の中に
許容できている状態のことをいいます。
簡単に言えば、普段 「自分はこういう人間です」 と言うことは自己概念です。
とは、つまり自分をそうだと認定(認識)していること。
これは、生まれ育って今の自分を形成してきた概念、思い込みなのです。
先の例に合わせてみたときに、
「自分は冷静沈着な人間です、どんな時でも動揺することはありません」
という概念があるとしましょう、
しかしある時に、とても素晴らしいドキュメンタリー番組を見ていて、
主人公の考えや行動に共感し、涙が一粒頬を流れた時でさえ、
「自分は冷静・・」 と思い込むような時には、「自己一致」はしていない、
ということです。
概念は内部要因よりは、外的要因によって形成される割合がとても多いです。
両親からの教え、学校の先生からの教え・・などなど。
「こうしなさい」 「・・・してはいけません」 「・・であるべきです」
こんな事柄が長年刷り込まれて、今の自分の概念として思っているのです。
「自分に正直にありたい」
下手をするとこの言葉は、一般社会的認知では 「わがまま」 とも取られかね
ないように思えます。
しかし、これは社会の一般的な概念から逸脱するということではなく、如何に
ありのままの自分として生きていくのか、ということだろうと思います。
ちょっと参考までに
このような内容を見て、どのように 「感じ」 ますでしょうか?
http://job.yomiuri.co.jp/interview/in...tm?ref=oss
_________________
●12月19日(土)
キャリアセミナーを開催いたします。
詳しくはこちらをご覧ください
↓
http://seplan.jp/pageevent.html
_________________
とは、今自分が体験していること、今実感していること
それが ”自分である” と感じることが、自分の概念の中に
許容できている状態のことをいいます。
簡単に言えば、普段 「自分はこういう人間です」 と言うことは自己概念です。
とは、つまり自分をそうだと認定(認識)していること。
これは、生まれ育って今の自分を形成してきた概念、思い込みなのです。
先の例に合わせてみたときに、
「自分は冷静沈着な人間です、どんな時でも動揺することはありません」
という概念があるとしましょう、
しかしある時に、とても素晴らしいドキュメンタリー番組を見ていて、
主人公の考えや行動に共感し、涙が一粒頬を流れた時でさえ、
「自分は冷静・・」 と思い込むような時には、「自己一致」はしていない、
ということです。
概念は内部要因よりは、外的要因によって形成される割合がとても多いです。
両親からの教え、学校の先生からの教え・・などなど。
「こうしなさい」 「・・・してはいけません」 「・・であるべきです」
こんな事柄が長年刷り込まれて、今の自分の概念として思っているのです。
「自分に正直にありたい」
下手をするとこの言葉は、一般社会的認知では 「わがまま」 とも取られかね
ないように思えます。
しかし、これは社会の一般的な概念から逸脱するということではなく、如何に
ありのままの自分として生きていくのか、ということだろうと思います。
ちょっと参考までに
このような内容を見て、どのように 「感じ」 ますでしょうか?
http://job.yomiuri.co.jp/interview/in...tm?ref=oss
_________________
●12月19日(土)
キャリアセミナーを開催いたします。
詳しくはこちらをご覧ください
↓
http://seplan.jp/pageevent.html
_________________
こんな偶然が・・
- 2009年11月 6日(金) 16:03 JST
-
- 投稿者:
- ゲストユーザー
-
- 閲覧数
- 3,096
「まさかこんな所で・・・!」
「同じ○○なんでびっくり!」
こんな、たまたま物語って結構あるものです。
実は私も、この1週間の間に2つもこんな驚きがありました。
実に、「なんという偶然!?」 と思えるようなことです。
キャリア理論を勉強する中で必ずやでてくるもので
「プランドハプンスタンスセオリー」
というものがあります。
これはクルンボルツ博士が提唱したもので、
日本語的には 「計画された偶然性理論」 といいます。
簡単にいうと、身に起こるものは単なる偶然ではなく、
そもそも計画されたいたというもの、換言すれば
必然的に、ということに近いです。
ただ、このままだと何か不思議な力の世界のように
見えますが、こう捉えるのが良いと思います。
我々が生きている中では、自分自身のこと、あるいは
家庭・家族のこと、またその周辺のことで様々なことが
起こります。
ことが起こればそれに直接・間接的に対処する必要が
あります。つまり、それについてどうするのか、どうすれば
良いのかを考え、そして行動をとることになります。
その結果として、事の発生の前後において少なからず
違った自分や環境が出来上がることになります。
ということは、その事のお陰で現時点の我々が存在
している、ということです。
故に、自分達の軌跡(キャリア)として、その事は
我々が呼び寄せ、起こしたものであるということです。
ただ、その偶然性を呼び込むためにも、我々は自ずと
行動することが必要だと思われます。
私の2つの驚きも、私がその場所、その人に会ったから
こそ、知り得た偶然だからです。
人生に発生する役割
- 2009年10月24日(土) 16:18 JST
-
- 投稿者:
- ゲストユーザー
-
- 閲覧数
- 2,204
人は生まれ、成長するにしたがい、その時々にこなす役割があります。
○子ども
→親との関係における自分です。乳幼児はこの役割が大部分です。
○学生
→学ぶという立場です。小中高大学生はもちろん、大人(職業人)
の習い事なども含まれます。
○職業人
→文字通り仕事をする立場です。バイトも職業人としての役割です。
○配偶者
→夫、妻としての役割です。
○家庭人
→親元を離れたところから始まる役割です。
○親
→子どもを持った時から始まる役割です。
○余暇を楽しむ人
→趣味やスポーツなど好きなことをして楽しむ時間です。
○市民
→社会を構成する一員として社会に貢献する、市民としての役割です。
以上は、キャリアの理論家である、ドナルド・E・スーパーが提唱した理論で
「ライフロール(キャリアの役割)」 というものです。
これは誰もが必ずこの役割を受け持ついうことはではありませんが、人によっては
いくつもの役割を同時期に持つことにもなります。
子供と学生 親と子供 市民と配偶者 など
つまり、役割は決して一つではないということです。もちろんその時に単独の
ものもあるかもしれませんが。
長い人生の中で、さまざまな役割を人はこなしていくことになります。
決して、今一時の意思決定において、その全てが決まるものでもありません。
その時々に悩み、考え、そして意思決定ができて行動をする。
その結果、いろんなことをこなしていけるのだろうと思います。
パソコンやロボットみたいな電子制御の機械は、誰かからその指示・命令を
インプットしてもらわなくては動くことができません。
対して人は、自分でいろんなことを考え、動くことができます。
だから、「悩む」 ことができるのです。
悩める生き物なのですから。
○子ども
→親との関係における自分です。乳幼児はこの役割が大部分です。
○学生
→学ぶという立場です。小中高大学生はもちろん、大人(職業人)
の習い事なども含まれます。
○職業人
→文字通り仕事をする立場です。バイトも職業人としての役割です。
○配偶者
→夫、妻としての役割です。
○家庭人
→親元を離れたところから始まる役割です。
○親
→子どもを持った時から始まる役割です。
○余暇を楽しむ人
→趣味やスポーツなど好きなことをして楽しむ時間です。
○市民
→社会を構成する一員として社会に貢献する、市民としての役割です。
以上は、キャリアの理論家である、ドナルド・E・スーパーが提唱した理論で
「ライフロール(キャリアの役割)」 というものです。
これは誰もが必ずこの役割を受け持ついうことはではありませんが、人によっては
いくつもの役割を同時期に持つことにもなります。
子供と学生 親と子供 市民と配偶者 など
つまり、役割は決して一つではないということです。もちろんその時に単独の
ものもあるかもしれませんが。
長い人生の中で、さまざまな役割を人はこなしていくことになります。
決して、今一時の意思決定において、その全てが決まるものでもありません。
その時々に悩み、考え、そして意思決定ができて行動をする。
その結果、いろんなことをこなしていけるのだろうと思います。
パソコンやロボットみたいな電子制御の機械は、誰かからその指示・命令を
インプットしてもらわなくては動くことができません。
対して人は、自分でいろんなことを考え、動くことができます。
だから、「悩む」 ことができるのです。
悩める生き物なのですから。